- 自分の年収でどのくらいの住宅ローンが組めるのかわからない
- 無理のない住宅ローンの返済計画を立てたい
- 住宅価格の上昇で購入に不安を感じている
結婚をきっかけにマイホームの購入を検討するようになる方は多くいます。住宅ローンを組んで住宅の購入資金に充てる場合、返済への不安を抱える方もいるのではないでしょうか。
この記事では年収に応じた住宅ローンの借入額や返済額の目安、無理なく返済するためのポイントを解説します。記事を読めば住宅ローンへの理解が深まり、自分の年収やライフプランに合った適切な借入額の目安がわかります。住宅ローンへの不安を解消し、マイホーム購入への一歩を踏み出しましょう。
年収に対する住宅ローンの目安は「年収の5〜6倍」

住宅ローンの借入額を考える際の目安として「年収倍率」があります。年収の5〜6倍が住宅ローンを無理なく返済できる金額とされています。年収650万円の場合、3,250〜3,900万円程度が住宅ローンの借入額の目安です。
ただし、実際の住宅ローンの借入可能額は金利や返済期間、頭金などにより変動します。年収倍率はあくまで住宅ローンの借入額の目安として理解しましょう。
年収に対する住宅ローンの返済比率の目安

住宅ローンを検討する際、年収倍率とともに重要な点が「返済比率」です。返済比率は額面年収に対する年間ローン返済額の割合を示す指標です。返済比率を意識せずに住宅ローンの借入額を決めると、毎月の返済が家計を圧迫する恐れがあります。年収に対する住宅ローンの返済比率について以下の内容を解説します。
- 住宅ローンの返済比率の一般的な目安は30〜35%
- 住宅ローンの理想的な返済比率は20〜25%
住宅ローンの返済比率の一般的な目安は30〜35%
多くの金融機関では住宅ローン審査における返済比率の上限を30〜35%に設定しています。返済比率とは年収に照らして返済可能とみなされる比率で、住宅ローンの上限額を推測するための目安です。
ただし、住宅ローンの返済比率の基準は税金や社会保険料控除前の年収(総支給額)である点に注意が必要です。住宅ローンの返済比率は手取りを基準とした返済負担とは感覚が異なる場合があります。
自動車ローンやカードローンなどの借入がある場合、年間返済額も含めて住宅ローンの返済比率が計算されます。住宅ローンの返済比率の30〜35%という数値は、あくまで金融機関が貸し出し可能と判断する上限です。必ずしも無理なく住宅ローンを返済できる水準とは限りません。
住宅ローンの理想的な返済比率は20〜25%
住宅ローンの返済比率は手取り年収の20〜25%に抑えることが理想的です。手取り年収に占める住宅ローンの返済比率を低く設定しておくことで、予期せぬ出費やライフプランの変化にも柔軟に対応できます。住宅ローンの返済比率を20〜25%に抑えるメリットは以下のとおりです。
- 子どもの教育費や車の買い替えなど、将来のライフイベントに備えやすくなる
- NISAやiDeCoを活用した資産形成がしやすくなる
- 趣味や旅行、自己投資など、生活の質を維持・向上するための支出を確保しやすくなる
- 金利上昇による返済額の増加に対応しやすく、家計への影響を抑えられる
住宅ローンの返済比率を理想的な範囲に収めれば住宅購入後の生活が豊かになり、精神的なゆとりを持てます。
【年収別】住宅ローンの借入可能額の目安

住宅ローンの借入可能額は年収によって大きく変動します。銀行は返済能力を年収で判断するため、年収が高い人ほど住宅ローンの借入可能額も増加します。年収別の住宅ローンの借入可能額の目安は以下のとおりです。
- 年収300万円:約1,500〜1,800万円
- 年収500万円:約2,500〜3,000万円
- 年収1,000万円:約5,000〜6,000万円
ただし、実際の住宅ローンの借入可能額は頭金や他の借入状況などにより異なります。
» 住宅ローンの事前審査でチェックされるポイントと通過するコツ
【年収別】住宅ローンの毎月の返済額の目安

住宅ローンを組む際は総借入額だけでなく毎月の返済額を具体的にイメージすることが不可欠です。年収に応じた無理のない住宅ローンの返済額の目安は、年収の約25%とされています。住宅ローンの返済額の目安は年収別に以下のとおりです。
- 年収300万円:約6.3万円/月
- 年収500万円:約10.4万円/月
- 年収800万円:約16.7万円/月
毎月の返済額の目安を参考に、ライフプランや家計状況に合わせて住宅ローンの返済計画を立てましょう。
住宅ローンを無理なく返済するためのポイント6選

住宅ローンの返済は将来の収支やライフイベントも踏まえて、多角的に計画を立てましょう。無理なく住宅ローンを返済するためのポイントは以下のとおりです。
- まとまった頭金を用意する
- 自分に合った金利タイプを選ぶ
- 固定資産税やその他の諸費用も考慮する
- 家計のバランスを意識した借入額を設定する
- 生活費や固定費の変動を考慮する
- 経済状況の変動を視野に入れる
まとまった頭金を用意する
住宅ローンを無理なく返済していくためには、まとまった頭金を用意する必要があります。頭金を用意すれば住宅ローンの借入額が減り、月々の返済や総利息を抑えられます。頭金を用意すると住宅ローン審査の通過率が高まり、有利な金利が適用されやすい点もメリットです。
計画的に住宅ローンの頭金を準備しておくことは、住宅購入後の生活を安定させるうえで重要です。
自分に合った金利タイプを選ぶ
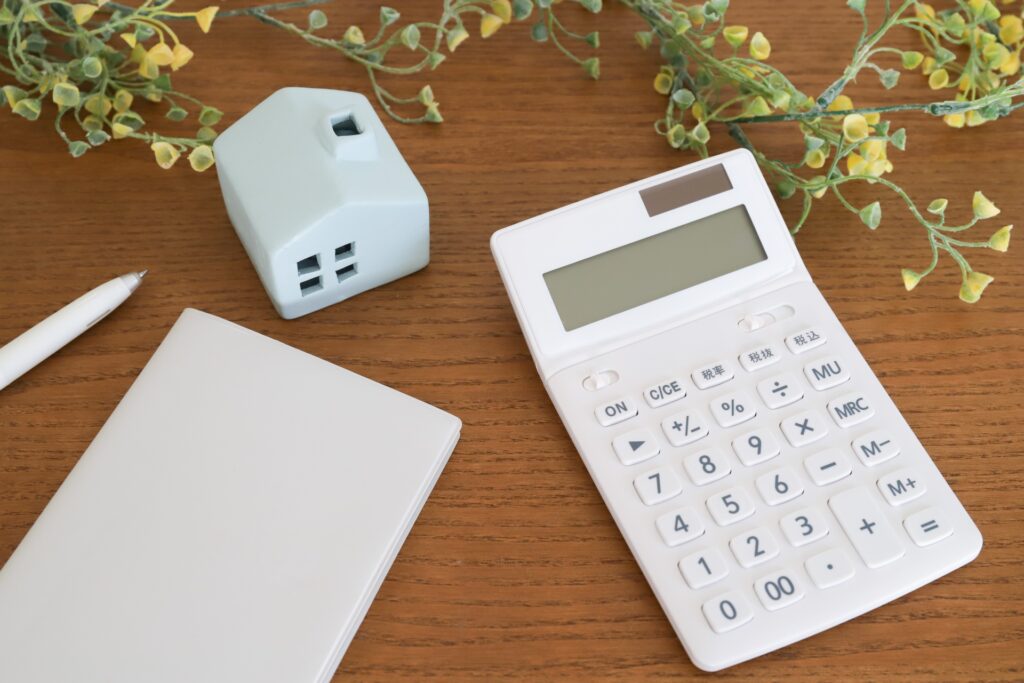
住宅ローンを無理なく返済するためには、ライフプランに合った金利タイプを選びましょう。金利タイプによって、住宅ローンの毎月の返済額や将来の総返済額が大きく変わってきます。住宅ローンの主な金利タイプは以下の4つです。
- 変動金利
- 変動金利は住宅ローンの借り入れ当初の金利が低く設定されています。ただし、変動金利は金利が上昇すると住宅ローンの返済額が増えるリスクがあります。金利上昇時にも繰り上げ返済できる余裕がある方や、住宅ローンの借り入れ当初の返済額をできるだけ抑えたい方に変動金利はおすすめです。
- 全期間固定金利
- 全期間固定金利は住宅ローンの返済が終わるまで金利と返済額が変わりません。住宅ローンの返済計画が立てやすく、将来の金利上昇リスクを避けたい方に全期間固定金利は適しています。子どもの教育費など、将来の支出の増加に備えたい場合にも全期間固定金利は安心です。
- 固定期間選択型金利
- 固定期間選択型金利は最初の一定期間だけ住宅ローンの金利が固定されます。子育て中など特定の期間だけ支出を安定させたい場合に固定期間選択型金利は有効です。固定期間選択型金利は、期間終了後に住宅ローンの金利が見直される点には注意が必要です。
- ミックスローン
- ミックスローンは変動金利と固定金利を組み合わせる方法です。変動金利と固定金利双方のメリットを生かしつつ、住宅ローンの金利変動のリスクを分散させたい場合にミックスローンは適しています。
収入や家族構成の変化を踏まえて最適な金利タイプを選ぶことが、無理のない住宅ローンの返済計画の鍵となります。
固定資産税やその他の諸費用も考慮する
住宅ローンの返済計画を立てる際は固定資産税やその他の諸費用も含めましょう。住宅を所有すると、住宅ローンの返済とは別に毎年の税金や建物のメンテナンス費用が発生します。税や諸費用を見落とすと、資金計画が大きく崩れる恐れがあります。
住宅ローン以外にかかる主な費用は以下のとおりです。
| 費用項目 | 内容 | 支払いタイミング |
|---|---|---|
| 毎年かかる税金 | 固定資産税や都市計画税 | 毎年 |
| 維持管理費 | マンション:管理費や修繕積立金 戸建て:外壁塗装や屋根修理のための修繕積立 | 毎月または数年ごと |
| 購入時の費用 | 仲介手数料や登記費用、不動産取得税や火災保険料 | 購入時 |
| リノベーション費用 | 中古物件の改装や工事費用 | 必要時 |
住宅ローン以外の費用をあらかじめ把握しておくことで、無理のない返済計画が立てられます。
家計のバランスを意識した借入額を設定する

住宅ローンの借入額は将来のライフプランや日々の生活まで見据え、家計全体のバランスを考えて設定しましょう。長期にわたる契約となるため、今の年収だけで住宅ローンの借入額を決めると家計を圧迫する恐れがあります。
住宅ローンで無理のない借入額を設定するためには、まず現在の家計を正確に把握しましょう。税金や社会保険料を引いた手取り額を基準に毎月の収入と支出を洗い出し、いくら貯蓄に回せるかを確認します。
住宅ローン返済後も家計に余裕を持たせるために、将来必要となる費用をあらかじめリストアップすることも大切です。代表的な項目は以下のとおりです。
- 教育費
- 車の買い替え費用
- 旅行や趣味のお金
- 生活防衛資金
ライフプランを事前に考慮すれば、無理なく返済を続けられる住宅ローンの借入額の目安がわかります。
生活費や固定費の変動を考慮する
住宅ローンの返済計画を立てる際には将来の生活費や固定費の変動をあらかじめ見込んでおきましょう。ライフステージの変化や時間の経過とともに、家計の支出は増える可能性があります。
住宅購入後の生活では以下の支出の変動が考えられます。
- 養育費や教育費
- 車の購入や維持費
- 管理費や修繕積立金
- 住宅設備の修繕や交換費
住宅ローンの返済中に世帯収入の減少や物価の上昇、増税が起こる可能性もあります。将来の変化を事前に考慮することが、安定的に住宅ローンを返済するための鍵です。
経済状況の変動を視野に入れる
住宅ローンを組む際は個人のライフプランだけでなく、将来の経済状況の変動も視野に入れましょう。金利や物価、景気といった社会全体の動きが長期にわたる住宅ローンの返済計画に影響を与える可能性があるためです。
勤務先の業績が景気に左右され、収入が変動することも考えられます。税制度の変更や不動産価値の下落といったリスクは、住宅ローンの返済中に十分に起こり得るものです。経済状況の変動を想定しておくことで不測の事態にも柔軟に対応でき、安心して住宅ローンの返済を続けられます。
年収が低く希望の住宅ローン借入可能額に届かない場合の対策

年収が低くて希望の住宅ローン借入可能額に届かない場合でも、諦める必要はありません。金融機関は返済能力を総合的に判断するため、以下の対策によって住宅ローンの借入可能額を増やせる可能性があります。
- 夫婦の収入を合算する
- ペアローンを活用する
夫婦の収入を合算する
夫婦の収入を合算して住宅ローンを申し込むと、希望額を借りられる可能性があります。夫婦の収入を合算する主な方法は以下のとおりです。
- 連帯債務
- 連帯債務とは夫婦がともに債務者となり、2人で1つの住宅ローンを返済する方法です。連帯債務を適用すると、夫婦がそれぞれの持ち分に応じて住宅ローン控除を利用できます。
- 連帯保証
- 連帯保証とは住宅ローンの主たる債務者は申込者本人で、配偶者は連帯保証人となる方法です。連帯保証の場合、住宅ローン控除は主たる債務者のみが利用できます。
夫婦の収入を合算すると住宅ローンの借入可能額を増やせますが、出産や育児などによる収入減には注意が必要です。長期的に無理なく住宅ローンを返済できるか十分に検討しましょう。
ペアローンを活用する
ペアローンは夫婦それぞれが個別に住宅ローンを契約し、互いに連帯保証人となることで世帯としての借入可能額を増やす方法です。2人分の収入をもとに審査を受けられるため、住宅ローン控除や団体信用生命保険などもそれぞれが利用可能です。
ただし、ペアローンを活用すると諸費用が二重に発生するデメリットがあります。ペアローンはライフプランとのバランスを考慮して、慎重に検討する必要があります。
住宅ローンと年収の目安に関するよくある質問

住宅ローンと年収の目安に関するよくある質問は以下のとおりです。
- 住宅ローンの年収倍率の具体的な計算方法は?
- 年収の10倍を借りることは可能?
住宅ローンの年収倍率の具体的な計算方法は?
住宅ローンの年収倍率は借入希望額を年収で割って求めます。年収600万円で3,000万円を借りる場合は「3,000万円÷600万円=5倍」です。住宅ローンの年収倍率の計算には税金や社会保険料控除前の額面年収を使用します。金融機関は源泉徴収票や確定申告書に書かれた金額をもとに住宅ローンの審査を行います。
夫婦で収入を合算するペアローンなどを利用する場合は、個人の年収ではなく世帯全体の年収で計算しましょう。
年収の10倍を借りることは可能?
個人の年収で住宅ローンを年収の10倍借りることは原則として不可能です。金融機関は住宅ローンの審査の際に返済比率を重視しており、返済比率が高すぎると返済リスクが高いと判断されます。一般的に住宅ローンの借入上限額は年収の7〜8倍程度です。
世帯年収を基準に住宅ローンの審査を受ける場合、個人の年収の10倍近い借入が可能な場合もあります。
しかし、仮に年収の10倍の住宅ローンを借入できたとしても、毎月の返済負担は大きくなります。安定した生活を守るためにも、無理のない住宅ローンの返済計画を立てることが重要です。
住宅ローンは年収の目安と返済比率を見極めて賢く借りよう

住宅ローンを賢く借りるには年収倍率と返済比率を把握する必要があります。一般的には住宅ローンの借入可能額は年収の5〜6倍、返済比率は30〜35%(理想は20〜25%)です。無理なく住宅ローンを返済するためのポイントは、頭金の準備や自分に合った金利タイプの選択、諸費用の計算などです。
年収が低く住宅ローンの借入希望額に届かない場合は、夫婦の収入を合算したりペアローンを組んだりする方法もあります。ただし、将来の収入減や生活費の増加、金利上昇といったリスクを踏まえて住宅ローンの借入額は慎重に判断する必要があります。
住宅ローンの返済が家計を圧迫しないようにするには、ライフステージに応じた将来の必要資金を見据えておくことが大切です。無理のない住宅ローンの返済計画を立て、マイホーム購入後も経済的に安定した生活を続けましょう。






コメント