マンション購入に必要な予算がわからず、悩む方は多くいます。どの程度の年収で、どのくらいの価格の物件が買えるのか、事前の確認が大切です。この記事では、年収に応じたマンションの購入予算の目安や、購入にかかる費用、購入時の注意点を解説します。
記事を読めば、自分の年収に合った適切なマンション購入予算を設定できます。無理のない購入計画を立て、経済的な不安を解消しましょう。
年収に基づくマンション購入予算の目安

年収に基づくマンション購入予算の目安を以下の項目別に解説します。
- 年収と借入可能額の関係
- 返済負担率の目安
年収と借入可能額の関係
マンション購入の予算を考える際、年収は重要な指標となります。一般的に、年収の4〜5倍が適切な購入予算です。年収600万円の場合、2,400〜3,000万円程度が予算の目安です。
年収以外にも、勤続年数や職種、他の借入状況などによって借入可能額は異なります。ボーナスの有無も、借入可能額が増える要因です。年収に加算して計算されます。共働きの場合は世帯年収で計算するため、借入可能額が増える可能性があります。
借入可能額は頭金の額によっても変動するため、できるだけ多くの頭金を用意したいところです。借入可能額の上限は、一般的に年収の7〜8倍程度です。ただし、借入可能額は金融機関によって異なるため、注意してください。
返済負担率の目安
年収に対する年間返済額の割合を「返済負担率」と言います。返済負担率は、住宅ローンの返済額が年収に占める割合を示す重要な指標です。一般的には、年収の25%以下が理想的な返済負担率とされています。30%を超えると、生活に支障をきたす可能性が高くなるため、注意しましょう。
35%以下は、金融機関が融資の上限とする目安です。共働き世帯の場合は、主たる収入の25%と従たる収入の20%を合わせた金額を目安にできます。返済負担率を計算する際は、ボーナス払いも考慮してください。将来の収入減少や支出増加を見込んで、余裕をもって計算しましょう。
返済負担率が高くなるほど、将来の金利上昇リスクに注意が必要です。無理のない返済計画で、安定的に住宅ローンを返済しましょう。
【年収別】購入可能なマンションのシミュレーション

購入可能なマンションのシミュレーションを以下の年収別に解説します。
- 年収300万円
- 年収500万円
- 年収700万円
年収300万円
年収300万円の場合、マンション購入の選択肢は限られますが、工夫次第で住宅取得の可能性はあります。借入可能額は年収の約5倍程度で、およそ1,500万円です。物件価格の目安は1,000〜1,500万円となります。1,000〜1,500万円の予算で購入できるマンションの条件は、以下のとおりです。
- 中古物件
- 古い築年数
- 駅から少し離れた立地
- 小さな間取り
- 郊外エリア
頭金は、物件価格の5〜10%程度(50〜150万円)が必要です。諸費用として、物件価格の5〜7%程度(50〜105万円)かかります。月々の返済額は6〜8万円程度になると予想されます。リノベーション物件も選択肢の一つです。古い物件を自分好みにリフォームすれば、予算内で希望に近い住まいを手に入れられます。
年収500万円

年収500万円の場合、マンション購入時の借入可能額は約2,500〜3,000万円です。一般的な返済負担率の目安である年収の25〜30%を基準にしています。物件価格の目安は3,000〜3,500万円程度です。都心部や人気エリアの場合、1〜2LDKの中古マンションが候補に上がります。
» 中古マンション購入時の注意点まるわかり!
郊外や地方都市では、2〜3LDKの新築マンションが候補となります。物件を選ぶ際は、頭金として物件価格の10〜20%程度を用意しましょう。諸費用として、物件価格の5%〜7%程度を見込んでください。マンション購入後は、月額2〜3万円程度の管理費や修繕積立金がかかります。
» マンションの管理費の相場とは?高額になる物件の特徴も解説
固定資産税や都市計画税などで、年間15〜20万円程度が必要となる点も押さえましょう。
年収700万円
年収700万円の場合、マンション購入予算の目安は4,000〜5,000万円程度です。借入可能額は、約3,500〜4,200万円程度になります。都心部や人気エリアでは1〜2LDKの中古マンション、郊外や地方都市では3LDK以上の新築マンションが候補となります。
頭金は、物件価格の10〜20%(400〜1,000万円)が理想的です。諸費用として物件価格の5〜10%も必要です。合計600〜1,500万円程度の自己資金を用意しましょう。返済負担率は、年収の25〜30%が目安です。年収700万円の場合、月々の返済額は約14.5〜17.5万円となります。
マンション購入にかかる費用

マンション購入にかかる費用は、以下のとおりです。
- 物件価格
- 頭金
- 諸費用
物件価格
マンションの物件価格は、立地や間取り、築年数によって大きく変わります。駅からの距離や階数、周辺環境なども価格が変わる要因です。都心部の物件は、郊外に比べて高価格になる傾向があります。東京23区内の新築3LDKマンションでは、5,000万円〜1億円以上の価格帯が多く見られます。(2025年現在ではkね1億円以上がかなり主要になってきていますね。苦しい…。)
一方、郊外の中古物件の場合、物件価格は3,000〜5,000万円程度です。最近の不動産市場では、都心部を中心に物件価格の上昇傾向が続いています。リノベーション済みの中古物件などは、比較的手頃な価格で良質な物件が手に入るためおすすめです。
物件価格は購入予算の中で最も大きな割合を占めるので、自分のライフスタイルや将来の計画に合わせて慎重に検討しましょう。
頭金

頭金の目安は、一般的に購入価格の10〜20%程度です。頭金を多く用意できると、借入額が減り、金利負担が軽くなります。より高額な物件を購入できる可能性も広がるためおすすめです。頭金が多いと、住宅ローンの金利が優遇される場合もあります。頭金0円での購入も可能ですが、審査が厳しくなる可能性があります。
頭金の準備には計画的な資金作りが大切です。積立や投資など、長期的な視点で準備を進めましょう。住宅ローン控除などの利用もおすすめです。
諸費用
マンション購入には、物件価格以外にも以下の諸費用がかかります。
- 不動産仲介手数料
- 登記費用
- 印紙税
- 住宅ローン関連費用
- 火災保険料
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税
- 引越し費用
- インテリア・家電購入費用
諸費用の合計は、一般的に物件価格の5~10%程度になります。3,000万円のマンションを購入する場合、150〜300万円程度の諸費用が必要になる計算です。諸費用は物件や状況によって異なるので、事前に不動産会社や金融機関に確認しましょう。
マンション購入後に発生する費用

マンション購入後に発生する費用は、以下のとおりです。
- 管理費・修繕積立金
- 固定資産税・都市計画税
管理費・修繕積立金
マンションを購入すると、管理費と修繕積立金を毎月支払う必要があります。管理費は、共用部分の清掃や設備の点検など、日常的な維持管理に使われます。月額3,000〜10,000円程度が目安です。修繕積立金は、将来の大規模修繕に備えて積み立てる費用で、月額5,000〜15,000円程度が目安となります。
» マンションの修繕積立金の疑問を徹底解説!
ただし、築年数が古い物件ほど高くなる傾向があるため、注意しましょう。適切な管理費と修繕積立金を支払っている物件は、長期的に見て資産価値が維持されやすいです。マンション購入時には、管理費と修繕積立金の費用も必ず確認しましょう。
» マンションの大規模修繕の必要性と工事開始までの流れ
固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は、マンション購入後に毎年支払う必要がある税金です。所有する不動産の価値に応じて課税されます。固定資産税は、土地と建物に対して課税される地方税です。都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられます。
税率は地域によって異なりますが、一般的に固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%程度です。毎年1月1日時点の所有者に課税され、通常は年4回に分けて納付します。マンションの場合、専有部分と共用部分の両方に課税されるので注意しましょう。新築住宅の場合は、一定期間税額が軽減される特例もあります。
マンション購入の際の注意点

マンション購入の際の注意点は、以下のとおりです。
- 無理のない返済計画を立てる
- 見落としがちな諸費用を確認する
- 想定外の出費に備える
- 将来の売却を視野に入れる
無理のない返済計画を立てる
将来の経済的な不安を軽減するために、無理のない返済計画を立てましょう。月々の返済額は年収の25%以下に抑え、返済期間は35年以内を目安にしてください。変動金利と固定金利のメリットとデメリットの比較も大切です。ボーナス払いを活用すると、月々の負担を軽減できます。
金利上昇のリスクも考慮してください。住宅ローンの借り換えオプションも視野に入れると、より柔軟に対応できます。将来の家族構成の変化にも備えましょう。子どもの誕生や教育費の増加など、ライフステージの変化に応じた柔軟な計画が必要になります。
返済シミュレーションツールを活用すると、具体的な計画を立てやすくなります。ファイナンシャルプランナーや銀行員など、専門家への相談もおすすめです。
見落としがちな諸費用を確認する

物件価格とは別に必要となる諸費用を事前に把握し、予算に組み込みましょう。諸費用を含めた総額を把握すれば、より現実的な予算計画を立てられます。見落としがちな諸費用は、以下のとおりです。
- 仲介手数料
- 登記費用
- 不動産取得税
- 印紙税
- 火災保険料
- ローン事務手数料
- 住宅ローン保証料
引越し費用やインテリア、家電購入費なども必要に応じて予算に組み込みましょう。中古物件の場合は、リフォームやリノベーション費用の検討も必要です。マンションによっては、駐車場の費用が必要な場合もあります。事前に諸費用の詳細を不動産会社や金融機関に確認し、余裕をもって資金を準備しましょう。
想定外の出費に備える
マンション購入後も安定した生活を送るために、想定外の出費に備えましょう。3〜6ヶ月分の生活費を貯金しておくと、突然の失業や病気など、不測の事態に対応できます。失業保険や生命保険などのセーフティネットを整えておくと安心です。変動金利を選択する場合は、金利上昇による返済額の増加も想定しましょう。
突発的な修繕や設備の故障に対応できる資金の確保も大切です。マンションの場合、共用部分の修繕積立金の値上がりにも備える必要があります。定期的に家計を見直し、必要に応じて支出を調整しましょう。住宅ローンの返済額以外に、毎月の貯蓄を確保しておくと、より安心してマンションを購入できます。
将来の売却を視野に入れる
資産価値の維持や向上が期待できる物件を選ぶと、売却時に有利になる可能性が高まります。マンションを購入する際に注目すべきポイントは、以下のとおりです。
- 立地や交通の利便性
- 人気エリアや将来性
- 築年数と管理状態
- 間取りや広さ
- リノベーション可能性
マンションの管理体制や修繕計画も確認しましょう。適切に管理されているマンションは、資産価値が維持されやすい傾向があります。周辺環境や開発計画も注目すべきポイントです。将来的に発展が見込める地域の場合、物件の価値が上がりやすくなります。売却時のターゲット層を想定して購入する方法もおすすめです。
子育て世帯向けの物件であれば、学校や公園が近くにあるかどうかも考慮しましょう。
マンション購入に関するよくある質問
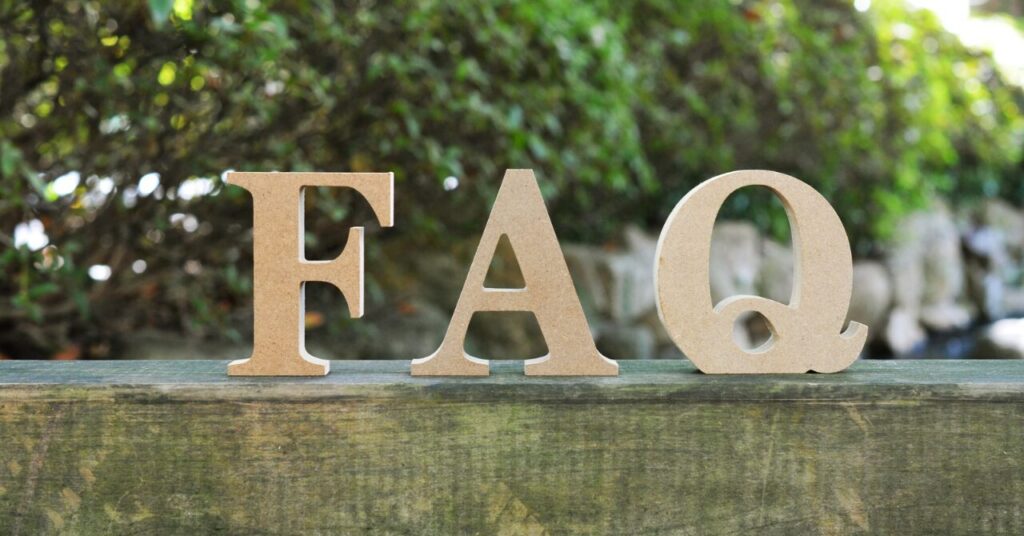
マンション購入に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 年収の何倍までのマンションが理想?
- 購入時に頭金はどのくらい必要?
- 中古と新築どちらが良い?
年収の何倍までのマンションが理想?
金融機関の融資審査基準に基づき、年収の4〜5倍程度のマンションが適切だと考えられています。ただし、頭金を多く用意できる場合や、将来的に収入増加が見込める場合は、年収の5倍を超えるマンションの検討も可能です。自分の生活スタイルや価値観に合わせて、無理のない判断をしましょう。
購入時に頭金はどのくらい必要?
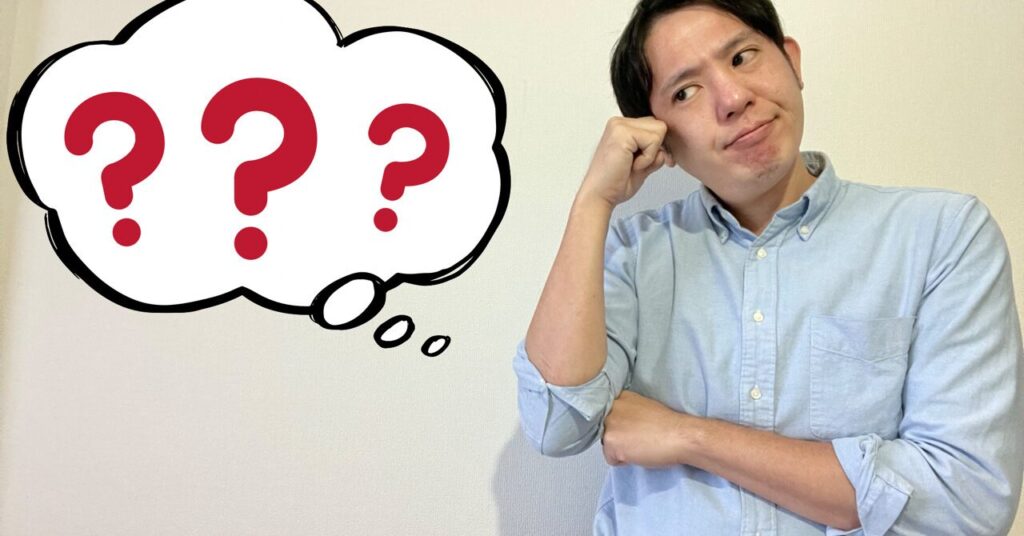
一般的に、マンションの購入価格の20〜30%程度の頭金が必要です。最低でも10%程度は必要になります。頭金の金額を決める際は、諸経費も考慮して計画しましょう。頭金を多く用意できると、借入額が減り、金利負担が軽くなります。頭金0円での購入も可能ですが、審査が厳しくなるので注意しましょう。
頭金が少ない場合は、民間金融機関のローンとフラット35の併用も選択肢の一つです。
中古と新築どちらが良い?
中古と新築には、メリットとデメリットがあります。新築の魅力は、新品の設備と自由な間取りです。最新の耐震基準や省エネ基準を満たしているので、安心感があります。しかし、初期費用が高く、立地の選択肢が限られる可能性があります。一方、中古は低めの価格が大きなメリットです。
» 耐震基準を満たすマンションを購入するメリットと確認方法
予算内で立地の良い物件を見つけやすくなります。リノベーションで好みの内装にできる点も魅力です。ただし、築年数によっては将来的な修繕費用が高くなる可能性があります。中古を選ぶ場合は、インスペクション(建物状況調査)が重要です。物件の状態を専門家に確認してもらうと、予想外の修繕費用を避けられます。
» 中古マンション買うなら築何年がベスト?上手な選び方を解説!
新築は資産価値の減少が早いですが、中古はすでに価格が下がっているため、影響が少ない点が特徴です。将来の売却を考えると、中古のほうが有利な場合もあります。予算や立地、設備など、自分にとって何を一番優先したいかを考えて選びましょう。両方の物件を見学し、比較検討してください。
» 築20年のマンションを購入する際のチェックポイント
まとめ

マンション購入の予算は、一般的に年収の4〜5倍程度が目安です。返済負担率は、年収の25%以下に抑えましょう。頭金は、物件価格の20%程度が理想的です。物件価格以外にも、諸費用や管理費、税金などの費用にも注意しましょう。中古と新築の選択は、予算や立地、ライフスタイルに応じて判断してください。
無理のない返済計画を立て、将来の売却も視野に入れましょう。資産価値の維持や向上が期待できる物件を選ぶと、売却時に有利です。疑問や不安がある場合は、専門家に相談しながら、じっくりと検討しましょう。






コメント